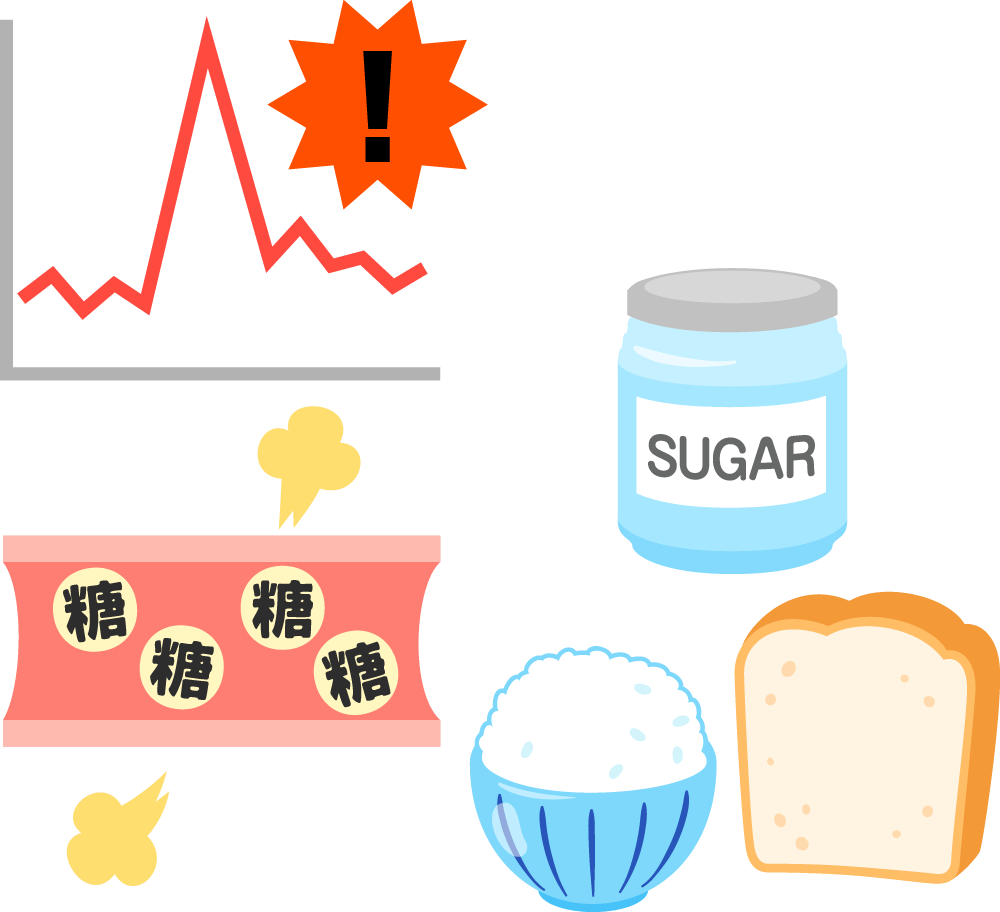健康診断や病院での血液検査で「クレアチニンキナーゼ(CK)の値が高い」と言われたときにはどのような状態が考えられるのでしょうか。いきなり高いと告げられると不安に感じることと思います。クレアチニンキナーゼが示すものや考えられる病気、受診の目安などについて説明します。
クレアチニンキナーゼとはどんな酵素?

クレアチニンキナーゼは、筋肉や心臓、脳に多く存在し、エネルギーの産生を助ける酵素です。筋肉が収縮するときには大量のエネルギーが必要で、その供給を支えるのがクレアチニンキナーゼの役割です。筋肉や心筋、脳の細胞が損傷するとクレアチニンキナーゼが血液中に漏れ出し、血中濃度が上昇します。
クレアチニンキナーゼの種類
クレアチニンキナーゼは部位によって3種類に分けられます。
- CK-MM:主に骨格筋に含まれるタイプです。
- CK-MB:心筋に多く含まれるタイプです。
- CK-BB:脳に分布するタイプです。
血液検査では総クレアチニンキナーゼ値を測定し、必要に応じてアイソザイム検査(同じ働きを持つ酵素の種類を細かく分けて調べる検査)を行い、どの部位が関与しているかを確認します。
一般社団法人 日本臨床検査専門医会 CK(クレアチニンキナーゼ)[ラボ NO.546(2024.7.発行)より]
クレアチニンキナーゼが高くなる原因
クレアチニンキナーゼが高くなる原因は病気だけではありません。日常生活の特定の状況でも起こることがあります。次のようなときに、クレアチニンキナーゼは高い状態になります。
激しい運動や筋トレの直後

強い筋肉の収縮や長時間の運動によって筋繊維が一時的に損傷した場合に、クレアチニンキナーゼが上昇します。
外傷や手術後
打撲や骨折、外科手術によって筋肉が損傷すると、血中のクレアチニンキナーゼ値が上昇します。
心筋梗塞や心筋炎
心筋が障害されることでCK-MBが増加すると、総クレアチニンキナーゼ値も上昇します。
脳の障害
脳梗塞や脳出血などではCK-BBが上昇する場合があります。
薬剤や代謝異常
一部の薬剤や甲状腺機能低下症などの代謝異常が原因になることもあります。
一般社団法人 日本臨床検査専門医会 CK(クレアチニンキナーゼ)[ラボ NO.546(2024.7.発行)より]
クレアチニンキナーゼが高いときに疑われる病気と受診の目安

クレアチニンキナーゼが高いときに考えられる病気には次のようなものがあります。
クレアチニンキナーゼが高いときに疑われる病気
心筋梗塞や心筋炎など心臓に関わる病気
心筋梗塞は心臓の血管が詰まって心筋が壊死する状態で、胸の痛みや呼吸困難を伴います。心筋炎はウイルスなど感染により心筋に炎症が起こる病気です。どちらも心筋細胞の障害によりCK-MBが増加します。
筋ジストロフィーなどの筋疾患
遺伝性の筋肉変性疾患で、筋肉が徐々に弱り変性していきます。CK-MMが慢性的に高い状態が続きます。
横紋筋融解症
激しい筋損傷によって筋肉の内容物(CKやミオグロビン)が血液中に流れ出す状態。筋肉痛、脱力感や腎不全の危険があり、早急な医療対応が必要です。
脳梗塞や脳出血などの脳疾患
脳の血流障害で起こる疾患。脳由来のCK-BBが上がる場合がありますが、血中総CKへの影響は少ないです。
病気を疑ったときの受診の目安
健康診断や検査でクレアチニンキナーゼの高値を指摘された場合でも、運動や軽い筋肉痛が原因で一時的に上昇することがあります。
しかし、胸の痛みや息切れ、強い筋肉痛、倦怠感、手足のしびれや動かしにくさなどの症状を伴う場合は、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。症状がなくても、数値が高い状態が続く場合は原因を特定するために追加検査を受ける必要があります。
一般社団法人 日本臨床検査専門医会 CK(クレアチニンキナーゼ)[ラボ NO.546(2024.7.発行)より]
まとめ
クレアチニンキナーゼは筋肉や心臓、脳の健康状態を示す重要な酵素です。高い場合には、運動や外傷などの一過性の原因から、心筋梗塞や筋疾患などの重篤な病気まで、さまざまな可能性があります。症状の有無や持続期間、他の検査結果と合わせて総合的に判断することが重要です。クレアチニンキナーゼの数値が高く、気になる症状があるときは医療機関で相談し、必要な検査を受けるようにしましょう。






 血糖値スパイクとは?糖尿病予備群が気をつけたい隠れ高血糖
血糖値がどのくらい高いと入院レベル?基準と症状の目安
血糖値スパイクとは?糖尿病予備群が気をつけたい隠れ高血糖
血糖値がどのくらい高いと入院レベル?基準と症状の目安