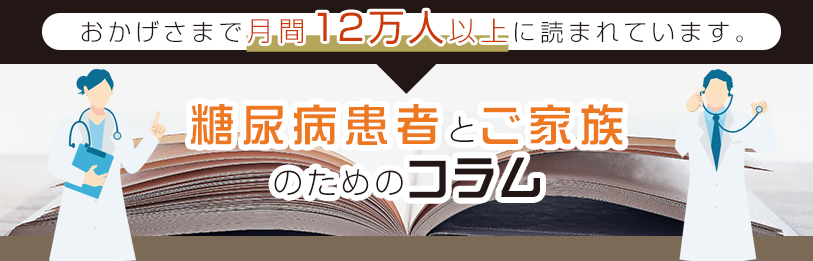
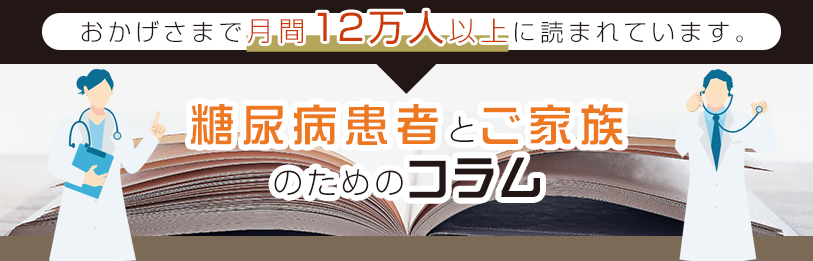
日本列島は火山帯の上に位置し、地震の多い国として知られています。また、毎年夏から秋にかけては、大きな台風もやってきます。日本のどこに住んでいても、絶対に災害に遭わないということはありません。 災害が起こった時に備えて、どのようなことが起こり…
続きを読む2017年11月に1型糖尿病患者の障害基礎年金が打ち切られるというニュースがあり、1型糖尿病や障害基礎年金について興味を持った方もいるのではないでしょうか?
1型糖尿病の基礎知識と障害基礎年金について詳しくみていきましょう。
生活習慣病を代表する糖尿病は、日本でも多くの人が患っています。糖尿病の怖さは自覚症状のないうちに進行し、命を脅かす様々な合併症をもたらすことです。
世界でも多くの人が糖尿病を患っています。糖尿病の世界情勢や世界ランキングをみていきましょう。
犬も人間のように糖尿病になるのでしょうか?人間の糖尿病は生活習慣から起こる2型糖尿病がほとんどですが、犬の場合は何が原因となるのでしょう。
糖尿病になった犬がどのような症状がみられるのか、治療は何を行うのか、どうしたら糖尿病を防ぐことができるのかについて詳しくみていきましょう。
愛猫も人間と同じように食べ過ぎが原因で糖尿病になることがあります。
愛猫を糖尿病から守るには糖尿病のことを知り、糖尿病にならないために予防すること、糖尿病になったら早めに適切な治療を受けることが肝心です。猫の糖尿病について一緒に勉強していきましょう。
犬猫の急性腎障害に対する治療の一つに透析治療があります。透析治療は失われた腎臓の機能を補う治療です。
障害された腎臓が良くなることはありませんが、透析治療によってペットの犬猫と過ごせる時間を延ばせることもあります。
透析治療はどのような治療なのか、どのような障害に対して行われるのか、犬猫の透析治療について詳しく見ていきましょう。
日本の糖尿病の人口は年々増えています。生活習慣が影響する2型糖尿病は40代以降の中高年・高齢者に多い印象がありますが、30代で若くして糖尿病になる人もいるのです。
30代の糖尿病はどのくらいいるのか、若くして糖尿病になる原因やどのような症状がみられるのか、糖尿病患者の平均寿命についてみていきましょう。
40歳以降の中高年や高齢者に多いとされている2型糖尿病ですが、最近では20代の若い糖尿病患者が増えていると言います。
その背景には、食生活が豊かになり、おいしいものが増えたことや、労働環境によって食生活の乱れが生じることが関連していると考えられています。20代が糖尿病になる原因や糖尿病の症状、平均寿命について詳しく見ていきましょう。
糖尿病患者の中には、「なかなか寝つけない」「眠りが浅くてすぐに目が覚めてしまう」「寝ても疲れがとれない」といった症状を訴える方がいます。こういった睡眠障害をもつ糖尿病患者は、決して少なくありません。
では、なぜ糖尿病患者は不眠に陥りやすいのでしょうか?不眠の原因を改めて知るとともに、快適な睡眠をとるための対策を見ていきましょう。
風邪を引いてしまったとき、まずは市販の風邪薬を飲んで治そうとする人が多いと思います。
しかし、この対処は糖尿病患者、特にインスリン注射や投薬で血糖コントロールを行っている場合は要注意です。薬効がぶつかり合って、危険な症状を引き起こしてしまうことがあるからです。
では、風邪薬に含まれているどのような成分に注意すべきなのでしょうか?
糖尿病の治療に使われる経口摂取薬(口から摂る薬)のなかで、近年注目されているのがDPP-4阻害薬です。
DPP-4阻害薬が日本で初めて発売されたのは2009年末のこと。まだ開発されて10年も経っていない新薬ですが、すでに多くの患者に処方されています。では、DPP-4阻害薬とはいったいどんな薬なのでしょうか?